ブリヂストン × Third Baseによる
路面データを活用した新規事業アイデアの事業性分析・PoCの推進
―事業開発を推進しながら、組織の自走力を強化する
Client:ブリヂストン

「よくここまでやったね」と役員から高評価─ ブリヂストンが“接点”を活かして挑む、新規事業の現在地とこれから
スピーカー紹介

株式会社ブリヂストン
ソリューション企画開発第1部長
氏名:脇山 雅史 様

株式会社ブリヂストン
ソリューション企画開発第1課長
氏名:根本 朋彰 様

株式会社ブリヂストン
ソリューション企画開発第1課
氏名:田邉 仁 様

(聞き手)株式会社Third Base
代表取締役
氏名:今村 将人
※ 部署名・役職は当時
プロジェクト発足の背景
社内でも重要な位置づけにある路面データ関連の新規事業開発。
事業開発を推進しながら、組織を強くする外部メンターが必要だった
Q(今村):今回構想されていたのは、路面との接点をもつ自社の強みを生かした路面データ関連のサービスでした。全社の中でどのような位置づけで、どのような期待を持たれていたのか、教えてください。
A(脇山様):当社はサステナブルなソリューション企業への転換を掲げています。
その中心にあるのが、当社のコア技術であるゴムやタイヤ、そしてそれらが接する“路面”というインフラを一体で捉えた価値創出です。タイヤと路面の接点を軸に、持続可能なモビリティ社会を実現する新たなソリューションを複数企画し、検討を進めています。
Q(今村):社内変革において、非常に重要な位置づけですね。そんな中で、Third Baseにご相談をいただいたのはどのような背景があったのでしょうか。
A(脇山様):タイヤを創って売るから、使っている間のお客様の困りごとを解決するソリューションを目指し新規事業開発をしてまいりました。
自分たちなりに事業開発のこと、お客様の困りごとを勉強していたつもりではあったものの、実際に事業開発を始めてみると知識だけでは難しいことがよく分かり、外部の知見を活用してはどうかと検討を始めました。
私たちは情報こそ集めていたものの、それらを基に事業開発を推進できていない点に課題を感じていました。私自身が具体的に事業内容に対して指示をすると押しつけになりかねませんし、押しつけを避けながら推進できるかというと難しさも感じていました。
そこで、答えを持って来るコンサルではなく、メンバーを育てながら事業を前に進めてくれる “先生”を探していました。もし私が一方的に進めたら、2人に何も残らない。自走できる力を残したかったのです。

株式会社ブリヂストン ソリューション企画開発第1部長 脇山 雅史 様
事業性分析の役員答申を完遂し、PoCフェーズへ移行。
納得するまで自身で考え抜いたからこそ、役員に自信を持って話せた
Q(今村):事業性分析の結果から事業戦略のストーリーを作り上げ、役員の方に次のステージへの移行承認をしていただくのが最初の取り組みでした。
元々皆さんが分析されていたところも多分にあった中で、どのように弊社のメンタリングサービスを活用いただいたか、またサービスへの所感について、お聞かせください。
A(根本様):メンタリングを活用し、これまで自社で調べ上げた情報と不足していた情報を整理し、事業戦略への落とし込みを行いました。外部セミナーで学んだ知識は、必ずしもそのままでは実務に適用することが難しいですが、メンタリングにより理解が深まり、実践を通して応用できるようになっていきました。
私たち一人ひとりの習熟度に合わせて、強化すべきポイントや、そのための思考プロセスを丁寧に示していただけたのは非常に有効でした。将来的に、自分たちだけで同じプロセスを回せる状態を目指しており、今回の支援はその土台を築くうえで大きな価値につながったと感じています。
通常のコンサルティングは「こうすべきだ」という結論だけを提示されがちですが、メンタリングでは自分たちが腹落ちすることを優先して検討を進めることができました。その結果、役員にも自信を持って話せましたし、自身の成長にもつながったと実感しています。
A(田邉様):週2回のメンタリングのうち、1回は事業の話をさせていただきました。競合分析などをどのように進めていくか、その結果をもって何をしていくかといった点を書き出して壁打ちしていました。ここで言う「壁打ち」とは、アイデアや意見を相手に聞いてもらうことを通じて、進展や改善を目指すプロセスのことです。この壁打ちをすることで、自分自身の理解を深めることにもつながりました。
もう1回は主に自身の能力開発の部分。事業を開発・計画していくスキルとして、自身に何が足りないか。どういった話し方をすると、チームメンバーや役員の方々に伝わるかといったスキルアップに使わせていただきました。メンタリングは、自分たちだけでは視野が狭まりがちなポイントを広げると言う意味でも良いきっかけになりました。
Q(今村):事業性分析の後はPoCフェーズへと移行しました。実際にPoCを実施されてみて、いかがでしたか。かなり試行錯誤がありましたよね。
A(根本様):想定はしていたのですが、実際にPoCをやってみると当初の期待ほどの効果を出せずに苦戦しました。また、我々の視点もある一点をターゲットにしていることに気づきましたし、俯瞰的にとらえたときにどんなサービスが考えられるか真剣に考えるフェーズに来たのだと実感し、我々のマインドも大きく変わるPoCになりました。
Q(今村):根本さんの熱量が更に増すのと同時に、冷静にやるべきことを捉え、整理されていたのが印象的でした。PoCに向けて事前に描いた計画も意味がありましたよね。
A(根本様):はい。PoC前に「何を見れば判断できるか」を徹底的に洗い出し、PDCAのPlanを固めておきました。現場では抜け漏れがないよう1つ1つチェックして実施しました。最も重要視したのは “ユーザーの表情”です。少しのシグナルも逃さないよう注意深く見るように心掛けました。現場での生の反応を踏まえサービス内容を検討できたのは今回が初めての経験です。机上で練った事業性と、現場で起きている事象の乖離は想像以上に大きいと痛感しました。第三者がどう感じるかに目を向けないとサービスは成り立たない。実際にサービスを使っていただき、「ここは効果が薄い」「ここは助かる」という生の声を収集できたのは非常に大きな成果でした。今回我々ではなく現場の方々がPoCを実施したことで、机上検討よりも進んだ実証になりました。

株式会社ブリヂストン ソリューション企画開発第1課長 根本 朋彰 様
週2回のメンタリング。60点の状態で持参して、その場で一緒にブラッシュアップするから、学習効果も大きいし、建設的な議論になった
Q(今村):週2回のメンタリング構成はどう感じられましたか。
A(田邉様):正直、最初は既存業務との両立が難しく感じたものの、既存業務があって後回しにしてしまうことも多々あったため、週2回と決められている方がそれをベースに組み立てられました。
毎回ここまでは調べましょうという点は明確にした上で、その結果をもって、壁打ちしながら深掘りという流れができたことで、独力では突破できなかったポイントを越えられた感覚がありました。
A(根本様):1回目=事業テーマ、2回目=自己スキルアップと役割を分けたのがとても良かったです。1回目の内容を自分たちで消化・内省し、翌週の1回目にさらに質を高めて臨める――このサイクルがフィットしました。
毎回整理をやり切った上でアドバイスをいただくというよりは、とりあえず60点の状態で持参して、その場で一緒にブラッシュアップする方が学習効果も大きかったし、建設的な議論にもなりました。
Q(今村):まさに、60点の段階で議論できるかが重要だと思っています。週2回の実施は珍しいとよく言われますが、週1回だとどうしても「本当に難しい部分」を一緒に考え切れずに議論がタイムアップしてしまうことが多いです。そのため、私自身は週2回の頻度に拘りを持っています。

株式会社ブリヂストン ソリューション企画開発第1課 田邉 仁 様
議論をその場で可視化。空中戦にならずに共通認識がすぐできる
Q(今村):私自身、メンタリングをさせていただく上で特に意識しているのは、議論を“その場で言語化・図解”し、空中戦を避けるということです。ミーティング後に「さて、次は何をすればいい?」と迷わないようにする、という狙いもあります。
A(根本様):あの進め方は皆の理解が早く議論もやりやすかったです。共通認識を即座に共有でき、その分、建設的な議論に時間を割くことができました。おかげさまで構造的に整理しながら考える習慣も身につきました。日常的なコミュニケーションにおいても必要不可欠なスキルだと感じています。
A(田邉様):議論内容をホワイトボードやスライドに即座に落とし込んでもらえるので、脱線が減り、深掘りもしやすい。振り返りもラクです。
実は形から真似していて、他のメンバーと「今村さんっぽいことしてますね~」と言いながら、少しずつですができるようになってきました(笑)
構造的なマトリクスを瞬時に、しかも話しながら整理できるのは本当にすごいと思います。

Q(今村):実は毎回けっこう緊張しながらやっています(笑)
もし、他にもお役に立てた点があれば教えてください。もっと褒めてください(笑)
A(田邉様):メンタリング後、議論の資料に加えて、テキストでコメントをいただけた点も良かったです。
自分で話しながらメモを取るのは難しく、また録音を聞き直すのも負担があるため、助かりました。
A(脇山様):目標に合わせて本プログラムの進め方を柔軟にカスタマイズしてもらえたのが助かりました。
決まった1〜2時間だけでなく、チャットで常に伴走してもらえた点も大きいですね。時間外までサポートいただき“お得感”がありました。他ではあまり聞かない手厚さです。
A(田邉様):“いつでも相談できる環境”があるうえで、週2回の対話もある。この手厚さはなかなかありません。
Q(今村):振り返ると、確かにかなりチャットもしましたよね。フラットに皆さんから意見や質問をいただけたので私も動きやすかったです。杓子定規に決められた回数のメンタリングを消化するのではなく、私自身も共に前に進めている感覚でした。皆さんの人柄も、検討されている事業テーマも、どちらも非常に魅力的で、ご一緒できて大変光栄でした。
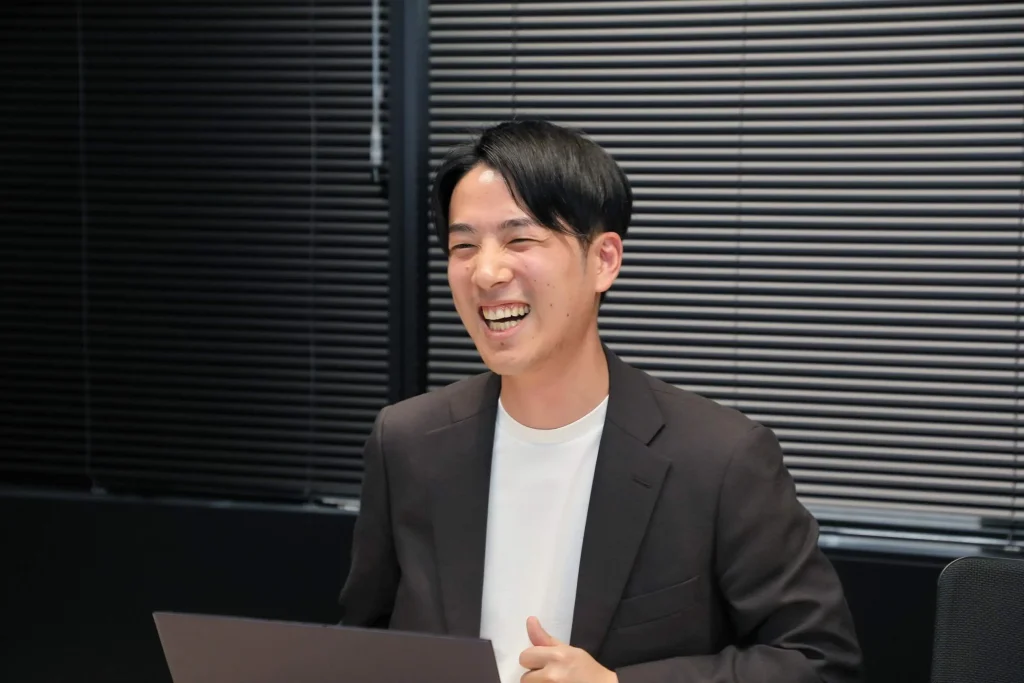
株式会社Third Base 代表取締役 今村 将人
過去に一度、プロジェクトが頓挫。強い危機感の中、役員に「よくここまでやった」と評価をいただくところまでやり切れた
A(脇山様):社内では一度プロジェクトが頓挫してしまい、「次こそは絶対に成功させたい」と強い危機感を抱いていました。自分の手だけでは限界があると感じ、メンターの力を借りる決断に至ったのもそういった背景からです。
最終的に経営層から「よくここまでまとめたね」と評価をもらえたのは大きな励みとなりました。
Q(今村):当時、本件の背景や社内における温度感を伺い、私も緊迫感を持って臨みました。根本さんと田邉さんの事業に対する熱い想いも知っていたからこそ、何が何でも決められた期限の中で戦略ストーリーを描き切らなければならないという覚悟でした。
とは言え、弊社は当時設立して1年と少しが経った程度のフェーズであり、お任せいただくには正直リスクや怖さもあったのではないでしょうか。
A(脇山様):これまで数多くの新規事業や共創の現場を見てきたので、人となりを見極める自信はありました。また、当社と同規模の企業への支援実績や、ARCHでのセミナー実績を確認できたことも安心材料でした。
実際に面談した際にも、我々の想いや課題を感じ取っていただき、レスポンスもしっかりいただけていた。面談で課題に即反応するレスポンスを見て「ここしかない」と判断しました。
Q(今村):皆さんに期待を持って任せていただき、大変感謝しています。
最後に、今後の展望・ブリヂストンさんが目指す世界観をお聞かせください。
A(田邉様):当社のコア事業はタイヤ事業ですが、タイヤやタイヤが使われているモビリティに着目したソリューションを作っていきたいです。モビリティの困りごとに留まらず、社会課題にまで視野を広げ、新規事業を開発していきたいと思っています。
A(根本様):コア事業であるタイヤ事業を成長させつつ、将来的にはサステナブルなソリューションカンパニーになることを目指しています。社会価値、顧客価値につながる新たな事業を創出する実行力がまだまだ不足していると感じております。これからは同じ志やマインドを持った人財を増やしていき、必ずやこの目標を具現化していきたいと思っています。
A(脇山様):タイヤ事業は引き続き成長させながら、第二の柱を築ければという想いからソリューションを検討してきました。
鍵を握るのは、内向きになりがちな視点を外に向けること。社外の方々とつながって、何に困っているか、どういう貢献ができるかをもっと見ていかないといけません。
現場の肌感覚でそういったことをもっとやってみようというスピード感とモチベーション・パッションが広がれば良いなと思っています。2人がそれを発信し、さらに社内のメンタリングまでやってくれたら非常に嬉しいなと思います。
Q(今村):本日はお時間をいただきまして、ありがとうございました!

インタビュー実績
Client:ブリヂストン
ブリヂストン × Third Baseによる 路面データを活用した新規事業アイデアの事業性分析・PoCの推進 ―事業開発を推進しながら、組織の自走力を強化する
Client:パーソルキャリア
パーソルキャリア×Third Baseによる 実務に直接伴走する1on1型研修 ―思考を構造化する習慣を身につけ、社内バイアスを取り払った「あるべき姿」を追求する
Client:DAIKEN
DAIKEN×Third Baseによる新領域事業開発と研究開発ビジョン策定の実現 ―対話重視の伴走で新領域の挑戦を推進し、研究開発ビジョンや事業化に確かな筋道を引く

 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 お問い合わせ
お問い合わせ


